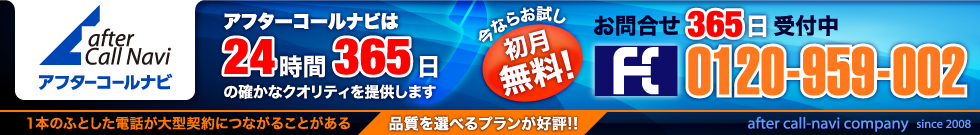お役立ち情報
もう迷わない!ビジネスで使える「お取り次ぎ」の正しい言葉と対応例

電話や来客対応の場面で、頻繁に行うのが「お取り次ぎ」です。
一見、単なる言葉のやり取りのように見えますが、実は企業の信頼を左右する重要なマナーです。
しかし現場では、「正しい言い方がわからない」「対応に時間を取られて業務が進まない」と悩む方が多くいます。本記事では、「お取り次ぎ」の正しい使い方から、業務効率を劇的に高めるプロの電話対応までを詳しく解説します。
「お取り次ぎ」とは?ビジネスの基本を押さえよう

「お取り次ぎ」は、ビジネスシーンにおいて、人や情報をつなぐ非常に重要な役割を果たします。まずは、基本となる3点を確認しましょう。
- 「お取り次ぎ」の意味:相手をつなぐ“橋渡し”の役割
- 正しい敬語の使い方:「お取り次ぎいたします」など定番4フレーズ
- 類似表現:「ご紹介」「ご連絡」との違いを理解する
以下で詳しく紹介します。
1.「お取り次ぎ」の意味:相手をつなぐ“橋渡し”の役割
「お取り次ぎ」とは、第三者の要件を担当者へ仲介・伝達する行為を指す謙譲語です。相手への敬意を示しながら情報を橋渡しすることが、お取り次ぎの本質です。
また電話口で「担当の者にお取り次ぎいたします」と伝えるだけで、相手への誠意と安心感を与えられます。ビジネスシーンでは、社内外の信頼関係を築く基本的マナーの一つといえるでしょう。
2.正しい敬語の使い方:「お取り次ぎいたします」など定番4フレーズ
状況に応じて言い回しを使い分けることで、より良い印象を与えられます。
代表的なフレーズは、以下の通りです。
| 言い回し | 使用シーンとポイント |
| お取り次ぎいたします。 | 最も基本的で汎用性の高い表現です。担当者へ電話や来客をつなぐ際に使用します。 「担当の〇〇にお取り次ぎいたします」のように、つなぐ相手を明確にするとより丁寧です。 |
| お取り次ぎしますので、少々お待ちください。 | 相手を待たせる場合に必ず添えたい一言です。相手への配慮を示すクッション言葉として機能し、丁寧な印象を与えます。 |
| お取り次ぎをお願いできますでしょうか。 | こちらから相手に担当者への仲介を依頼する際の表現です。 例えば、訪問先で担当者がわからない場合に「〇〇の件で担当の方にお取り次ぎをお願いできますでしょうか」と使います。 |
| お取り次ぎさせていただきます。 | 「お取り次ぎいたします」よりも、さらに謙虚で丁寧な印象を与える表現です。相手が目上の方や重要な取引先の場合に適しています。 ただし、過剰な敬語は回りくどくなるため、相手との関係性に応じて使い分けましょう。 |
それぞれの場合に応じて、適切に使い分けられるようにしましょう。
3.類似表現:「ご紹介」「ご連絡」との違いを理解する
「お取り次ぎ」には似たような表現があり、誤って使うと意図が正しく伝わらない可能性があります。特に「ご紹介」と「ご連絡」との違いを理解し、適切に使い分けることが重要です。
| 表現 | 意味とニュアンス | 使い分けのポイント |
| お取り次ぎ |
二者間の「仲介・橋渡し」をすること。 AさんからBさんへの電話や伝言を、Cさん(自分)が間に入ってつなぐ行為を指します。あくまで中立的な立場での伝達です。 |
担当者が別にいる場合に、その担当者へ電話や要件をつなぐ際に使います。 |
| ご紹介 |
人や物を他者に「推薦」すること。 人を紹介する場合、その人の信頼性や利点を伝えて推薦するニュアンスが含まれます。 |
新しい取引先を紹介してもらったり、自社の担当者として誰かを推薦したりする場合に使います。 |
| ご連絡 |
一方向的に「情報を伝える」こと。 相手に何かを知らせるための行為であり、双方向のやり取りや仲介の意味合いは含みません。 |
報告・連絡・相談(報連相)など、こちらから情報を伝える際に使います。 |
状況に応じて表現を選ぶことが、ビジネスマナーの基本です。
シーン別:「お取り次ぎ」の正しい使い方と例文集

「お取り次ぎ」は、電話やメール、対面など、ビジネスのさまざまなシーンで登場します。具体的なシーン別の模範フレーズと例文をみていきましょう。
- 【電話対応】担当者への取り次ぎ・不在時の言い方
- 【メール】転送依頼や引き継ぎの際に使える文例
- 【伝言メモ】要件を丁寧に伝える際の書き方
- 【お礼表現】「お取り次ぎいただきありがとうございます」
- 【NG例】「代わります」など、無意識に使いがちな誤用
以下で、詳しく紹介します。
1.【電話対応】担当者への取り次ぎ・不在時の言い方
電話対応は企業の顔ともいえる重要な業務です。担当者へスムーズに取り次ぐ場合と、あいにく不在の場合では、伝えるべき内容と表現が異なります。常に丁寧な言葉遣いを心がけ、相手に不安を与えない対応が求められます。
担当者へ取り次ぐ時
担当者不在時
電話口で「お取り次ぎ」を行う際は、保留時間にも配慮しましょう。
2.【メール】転送依頼や引き継ぎの際に使える文例
受け取ったメールの担当が自分ではない場合、送信者に対して失礼のないように担当者への転送を依頼したり、適切な担当者を案内したりする必要があります。要件を正確に伝え、迅速な対応を促す丁寧な表現が重要です。
件名:【株式会社〇〇】お問い合わせの件(担当者への転送のお願い)
株式会社△△
営業部 □□様
平素より大変お世話になっております。
株式会社〇〇の佐藤です。
この度は、お問い合わせいただき、誠にありがとうございます。
大変恐縮ながら、お問い合わせいただいた〇〇の件につきましては、担当が別の者となります。
つきましては、本メールを担当部署へ転送し、後ほど改めて担当者よりご連絡させていただきます。
恐れ入りますが、今しばらくお待ちいただけますようお願い申し上げます。
メールでの「お取り次ぎ」においては、「誰から誰に」「どのような要件で」依頼があったかを、新しい担当者へ正確に伝達することを徹底しましょう。
3.【伝言メモ】要件を丁寧に伝える際の書き方
手紙や伝言メモで、第三者へメッセージを託す場合にも「お取り次ぎ」の表現が役立ちます。相手の手を煩わせることへの配慮を示しつつ、用件を明確に伝えることが大切です。
手紙での依頼文例
伝言メモでの依頼文例
伝言メモを作成する際は、「誰から」「いつ」「どのような要件で」依頼されたかを5W1Hで明確に記載することを意識しましょう。
4.【お礼表現】「お取り次ぎいただきありがとうございます」
誰かに仲介をしてもらった際には、感謝の気持ちを伝えることがビジネスマナーです。特に、自分のために手間をかけてもらった場合には、丁寧にお礼を述べることで、良好な人間関係を維持できます。
口頭で伝える場合
メールで伝える場合
感謝の気持ちを伝える際は、「何のおかげで助かったのか」と具体的な効果を添えるとより気持ちが伝わるでしょう。
5.【NG例】「代わります」など、無意識に使いがちな誤用
良かれと思って使った言葉が、実は相手に失礼な印象を与えてしまうケースがあります。NG例を知り、正しい代替フレーズを身につけ、コミュニケーションの質を高めましょう。
| NG例 | 理由と問題点 | 代替フレーズ |
| 「〇〇さん、いらっしゃいますか?」 | 「いらっしゃる」は尊敬語であり、身内である社内の人間に対して使うのは不適切 | 「〇〇はおりますでしょうか?」 |
| 「取り急ぎお礼まで」 | 「取り急ぎ~まで」という表現は、本来の詳細な報告を省略した略式の言い方です。目上の方に使うと失礼にあたる可能性があります。 | 「まずはお礼を申し上げたく、ご連絡いたしました。詳細は改めてご報告します」 |
| 「担当者に伝えておきます」 | 「~ておく」という表現は、相手によってはぞんざいな印象や、上から目線のニュアンスで受け取られることがあります。 | 「担当の者に申し伝えます」 |
敬語の誤用や状況に合わない表現を避けるようにしましょう。
電話対応の現場で起きている「お取り次ぎ」3つの課題

一見単純に見える「お取り次ぎ」業務ですが、現代のビジネス環境においては、企業の生産性や成長を妨げる深刻な課題を内包しています。以下では、3つの課題を紹介します。
- コア業務の中断:1本の電話が集中を奪う
- 機会損失:取りこぼしや対応漏れのリスク
- 応対品質のばらつき:教育コストの増加
3つの課題について、詳しくみていきましょう。
1.コア業務の中断:1本の電話が集中を奪う
多くの企業にとって、電話対応は本来の業務を中断させる最大の要因の一つです。一度中断されると、集中力を取り戻すのに多くの時間と精神的エネルギーが必要になります。
研究によれば、一度作業を中断されると、元の作業に戻るまでに平均して15分以上かかるデータもあります。この「中断コスト」が積み重なることで、従業員一人ひとりの生産性は著しく低下し、結果として企業全体の業務効率が悪化するのです。
2.機会損失:取りこぼしや対応漏れのリスク
ビジネスチャンスは、必ずしも企業の営業時間内に訪れるとは限りません。営業時間外や休日にかかってきた一本の電話が、大きな契約につながる可能性も十分にあります。
しかし、多くの企業では、時間外の電話対応体制が整っておらず、潜在顧客からの問い合わせを取りこぼしているのが現状です。また、繁忙期に電話が殺到し、対応しきれずにあきらめてしまうケースも少なくありません。
3.応対品質のばらつき:教育コストの増加
電話応対は、企業の「顔」として顧客が最初に接する窓口です。しかし、担当する社員によってスキルや知識に差があると、応対品質にバラつきが生じ、顧客に不安や不満を与えてしまいます。
不適切な対応は、クレームの原因になるだけでなく、企業のブランドイメージを大きく損なうリスクもはらんでいます。全社員に対して均一かつ質の高い電話対応教育を行うには、多大な時間とコストがかかるのが現実です。
【アフターコールナビ】が実現する「プロのお取り次ぎ」3つの強み

「お取り次ぎ」業務の深刻な課題は、プロの電話代行サービスを活用することで解決できます。電話代行サービス「アフターコールナビ」の特徴について紹介します。
- 専門教育を受けたオペレーターによる正確で丁寧な対応
- 独自システムで実現する迅速・正確な情報伝達
- 営業電話をフィルタリングする選別スキル
以下で詳しくみていきましょう。
1.専門教育を受けたオペレーターによる正確で丁寧な対応
多くの中小企業では、担当社員によって電話応対のスキルに差が出ることが課題です。しかし、アフターコールナビのサービスでは、専門的な教育を受けたプロのオペレーターが一貫して対応します。
これにより、社員教育にかかるコストや時間を削減しながら、常に均一で質の高い「お取り次ぎ」を実現可能です。クレームや対応ミスを防ぎ、顧客からの信頼を獲得できます。
2.独自システムで実現する迅速・正確な情報伝達
ビジネスチャンスは、迅速かつ正確な情報伝達にかかっています。営業時間外や担当者不在時に電話がかかってきた場合、情報が滞ると機会損失につながりかねません。
アフターコールナビは独自のシステムを活用し、受けた電話の内容を即座に整理し、設定されたルールに従って担当者へ迅速かつ正確に通知します。これにより、時間や場所を問わず、重要な連絡を取りこぼすリスクを最小限に抑えられます。
3.営業電話をフィルタリングする選別スキル
業務を中断させる大きな要因が、不要な営業電話や間違い電話です。電話代行サービスは、これらの電話を的確に選別し、遮断する「フィルター」としての役割も果たします。
あらかじめ設定したルールに基づき、オペレーターが必要な電話と不要な電話を判断し、重要な用件のみを担当者へおつなぎします。これにより、社員が煩わしいセールス電話に時間を奪われることなく、本来集中すべきコア業務に専念できるでしょう。
まとめ

「お取り次ぎ」とは一見単純な業務にみえますが、生産性の低下や機会損失・企業イメージの悪化など、ビジネスの成長を阻害する深刻な課題が潜んでいます。これらの課題を解決し、従業員が本来注力すべきコア業務に集中できる環境を整える最も効果的な手段が、プロの電話代行サービスです。
ぜひこの機会に、貴社の未来を切り拓くパートナーとして、アフターコールナビのような高品質な電話代行サービスの導入をご検討ください。
【Q&A】
- 「お取り次ぎ」と「転送」はどう違いますか?
「お取り次ぎ」は、第三者の要件を担当者へ仲介・伝達する行為を指す謙譲語です。一方、「転送」は、電話回線やメールを物理的・技術的につなぎ替える行為を指します。お取り次ぎは「人が介在する丁寧な橋渡し」であり、転送は「システムによる自動的な接続」の点で異なります。
- 電話代行サービスを導入すると「お取り次ぎ」はどのように行われますか?
専門教育を受けたオペレーターが応対します。内容をヒアリングし、あらかじめ設定されたルールに基づき、緊急度や要件に応じて担当者にメールやチャットなどで正確に情報伝達を行います。
不要な営業電話などはここでフィルタリングされるため、社員は必要な情報のみを受け取ることが可能です。